当メディア『Synchronic』 では、
様々な教材(書籍/プログラム等)を紹介&販売をしていくわけですが、
その前段階でご理解いただきたいことをまとめました。
それが、全5話に渡ってお届けする、
『
いわば、学習のための学習法です。
今回はその第1話ということで、以下の内容でお届けします。
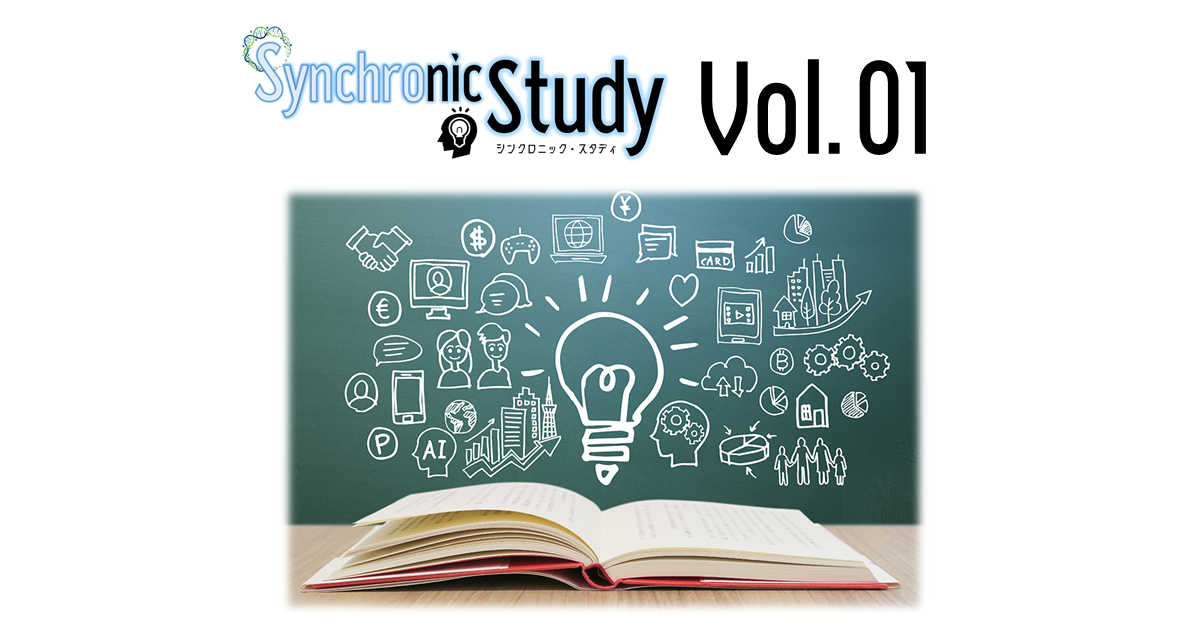
当メディア『Synchronic』 では、
様々な教材(書籍/プログラム等)を紹介&販売をしていくわけですが、
その前段階でご理解いただきたいことをまとめました。
それが、全5話に渡ってお届けする、
『
いわば、学習のための学習法です。
今回はその第1話ということで、以下の内容でお届けします。
20代の頃にフリーランスの「ゴーストライター」として独立。これまで数多くの執筆代行/コンテンツ制作代行等を手掛けてきた。近年は、和の『叡智』に感銘を受け、シンクロニスト/東洋哲学伝承師として活動している。≫詳細プロフィールはコチラ